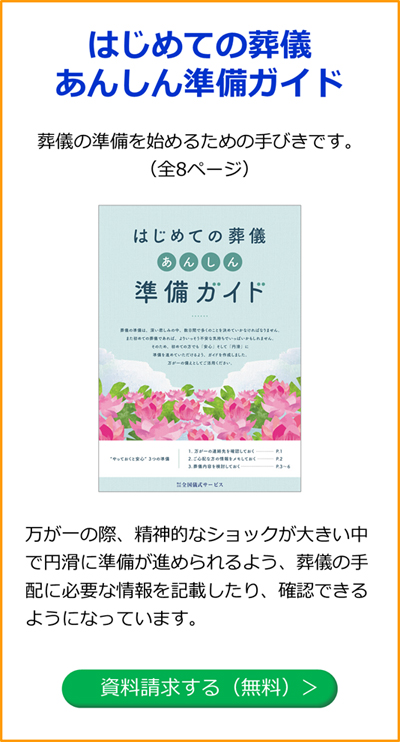末期の水と湯灌、身支度から納棺までを解説
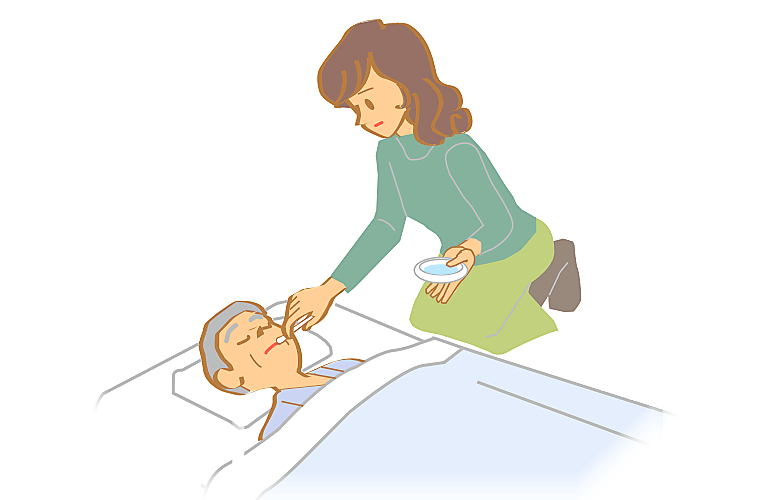
2024年1月22日更新。
亡くなってから故人を棺に納めるまでの間には、「末期の水」から始まる大切な儀式があります。古来より伝わるこれらの儀式とはどのようなもので、どういった意味があるのでしょうか。故人が安らかに旅立てるように知識を深めましょう。
【もくじ】
1.末期の水とは
2.遺体を清める
3.死化粧をほどこす
4.死装束に着替えて整える
5.枕元で行う読経 ~ 枕経 ~
6.納棺の際の注意点
1.末期(まつご)の水とは
「末期の水」は、臨終の際に取る「死に水」のことです。末期の水の由来は諸説ありますが、お釈迦様が亡くなる前に弟子にお水を求めたことが由来とされています。
方法としては白筆か割り箸の先に脱脂綿をくるみ、血縁の濃い順に故人の唇を湿らせます。準備が間に合わない場合は新しいガーゼなどで代用することもあります。
病院で亡くなった場合は、緊急の措置として病人用の水飲みで故人の唇を潤す場合もあるようですが、故人を自宅へ運んでから改めて死に水を取るのが一般的なようです。末期の水は、後から来た人のために枕飾りの横に置いておきます。
2.遺体を清める ~ 清拭と湯灌(ゆかん)の違い ~
医師によって死亡が確認されたら病院で遺体を清めてくれることがありますが、これは清拭といい衛生面の意味から看護士が遺体をアルコールで清めるもので、湯灌とは異なります。
湯灌は故人の成仏を願って行う宗教的な意味があり、遺族の気持ちや願いを反映した儀式です。
湯灌(ゆかん)の儀
「湯灌」とは、故人の体を家族が洗い清めるという古来からの儀式です。これは故人の生前の穢れや苦しみを洗い清めるとともに、生に対する煩悩を断ち、来世の高徳を願いながら執り行う、とても精神性の高いしきたりです。
かつては、たらいに入れた水にお湯を足して温度調節した「逆さ水」で遺体を清めていました。
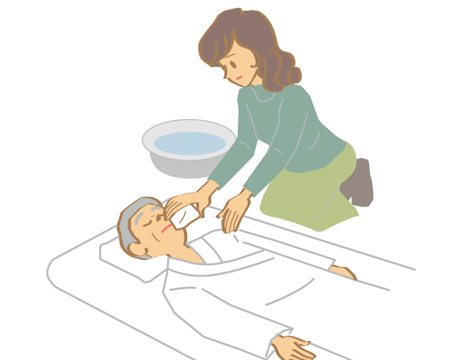
3.死化粧をほどこす
湯灌が済むと、死化粧をして身づくろいをします。爪を切り揃え、髪も整えます。さらに男性はひげをそり、女性には薄化粧をします。
4.死装束に着替えて整える
死化粧が済むと、故人を死装束に着替えさせます。これは仏式での冥土への旅装束のことです。
装束としては、経帷子(きょうかたびら)・三角頭布・頭陀袋・手甲・脚絆・白足袋・数珠・六文銭・わら草履・編み笠・杖などがあります。
着物は左前に着せるなど、通常とは逆の着方で着付けます。本来は白無地の木綿で縫った経帷子を着せますが、最近は故人が生前に好んだ衣服(柄物も可)や新しい浴衣などを着せ、納棺の時に葬儀社が用意した経帷子で遺体をおおうという場合も多いようです。
宗派によっても違いがあるので、事前に菩提寺や葬儀社に確認しておきましょう。
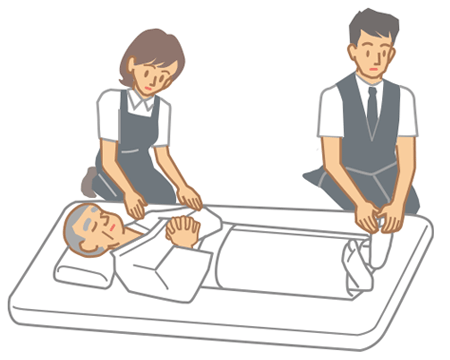
一般的な死装束の例
笠
頭巾
数珠
頭陀袋(ずだぶくろ)・六文銭(ろくもんせん)
白足袋
経帷子(きょうかたびら)
手甲(てっこう)
脚絆(きゃはん)
草履
杖
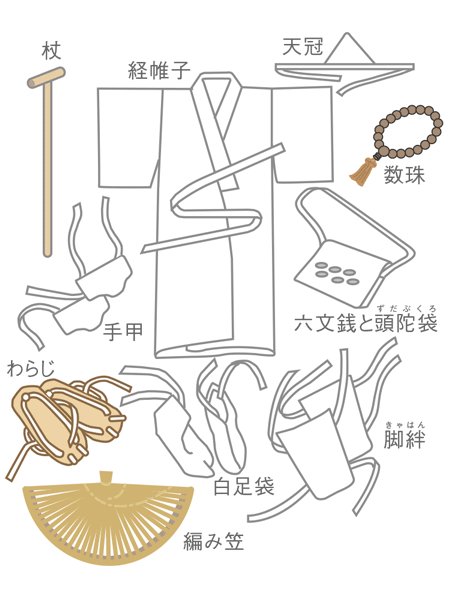
5.枕元で行う読経 ~ 枕経 ~
枕経とは、仏式において死者を納棺するのに先立ち、枕元で行う読経です。宗派によっては、剃髪(ていはつ)や授戒(じゅかい)をするところもあります。今日では枕経を行う喪家は少なくなりました。
6.納棺の際の注意点
納棺とは故人を棺の中に納めることです。仏式であれば納棺前に死装束(しにしょうぞく)に着せ替え、死化粧をします。
故人にはドライアイスを添えますが、火葬の関係上、「CO2・ダイオキシン発生の原因になる石油化学製品」や「カーボン製品などの火葬炉設備の故障の原因となるもの」、「遺骨の損傷原因の可能性がある金属製品やガラス・陶器」、「ライターや缶飲料」などは棺の中に納めることはできません。
また、燃焼物であっても「書籍」や「大型の果実類」、「ぬいぐるみなどの大型繊維製品」は火葬場から断られることがあります。
棺に納めるものは葬儀社などに確認をとってから納めるようにしましょう。
神式での納棺
神官が立ち会うのが正式ですが、最近は遺族と葬儀社だけで行うことが多いようです。納棺後、遺体を安置し、喪主から順に、二礼二拍手一礼を忍手(しのびて)で行います。
キリスト教での納棺
納棺の際は神父(プロテスタントでは牧師)が立ち会うのが一般的です。神父または牧師が祈りの言葉を捧げたあと、遺族の手によって遺体を納棺します。
※この記事は首都圏での葬儀における標準的な例です
目次に戻る
24時間365日、ご相談を受け付けております。
早朝・深夜、祝日・連休・年末年始も、気兼ねなくご連絡ください。
全国儀式サービス コールセンター
■お電話
0120-491-499
(通話料・相談料・紹介料、無料)
■メール
お問い合わせページから相談する