いざという時にも仲々、人には聞けない葬儀用語や知識、マナーをわかり易く解説しています。
人生の旅立ちをしめやかにお見送りするために、「儀式大辞典」をお役立てください。
葬儀全体の流れ ※首都圏の例です。
いざ葬儀が発生いたしますと、しなければならない事が波のように押し寄せます。悲しみに浸る暇もなく、次から次へと弔問客が訪れ、気を取り直し今後の全ての対応に向かわなければなりません。喪主を経験したことがない方に、スムーズに葬儀を執り行ってもらうために、葬儀の流れを17項目に分類致しました。
打ち合わせ
から通夜開始

通夜から
告別式
-
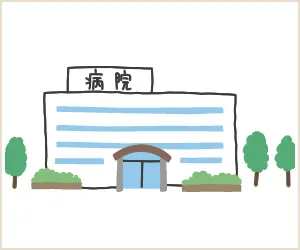
0.危篤
命に危険が迫り、予断を許さない状態のことを言います。病院から危篤の連絡を受けた場合、親族や職場へ危篤である旨の連絡をして、その後、病院へ急いで向かいます。
-

1. ご臨終直後
3大疾患を始め救急など、お亡くなりになる場所の約8割が病院となっています。その際、病院からはご遺体をどちらかに移送いただくことが求められます。(※「4.病院からのご遺体のお帰り先」をご覧ください)
-

2. 葬儀社を手配する
病院によっては病院に出入りしている葬儀社がいる場合がございますので、会社の福利厚生契約で、決まった葬儀社がある旨をお伝えいただき、一番初めに、葬儀支援サービスのコールセンターにお電話ください。
-

3. 死亡診断書をもらう
「死亡診断書」と一緒になっている「死亡届」を 7日以内(ご葬儀が営まれる前日まで)に 役所の窓口(24時間受付)に提出しなければいけません。
-
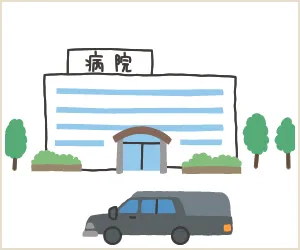
4. 病院からのご遺体のお帰り先
事前にお帰り先をお決めいただくと移送が円滑になります。
-
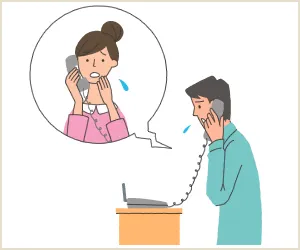
5. 死亡の連絡
関係者に死亡を知らせます。
-

6. ご遺体を安置する
ご遺体を安置し、枕飾りを供えます。
-

7. ご葬儀の打合せ
ご安置の後、お参りをしていただき、その後ご葬儀の打合せとなります。
-

8. 納棺
納棺は打合せ後、近しい身内が揃ってから行います。通夜まで日にちが空く場合は、通夜の少し前に行うのが普通です。
-
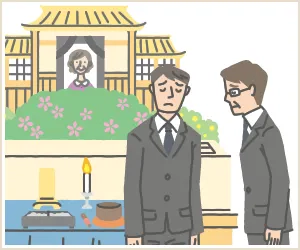
9. 通夜
通夜とは、ご遺族や近親者が故人に最後の別れを告げ、冥福を祈る儀式です。今は2時間程度(宗派によっても違いますが、僧侶の読経は30~40分程度です)で終わる半通夜が一般的となりました。
-

10. ご葬儀と告別式
ご葬儀と告別式は本来、別の儀式です。ご葬儀は、故人の成仏を祈るためにご遺族や近親者が営む儀式。告別式は、故人と親交のあった人たちが故人に最後の別れを告げる儀式です。しかし最近では、よほど大規模なご葬儀でない限り、この2つを区別せず、親族のあと、会葬者がすぐに焼香を行うことが多いようです。
-
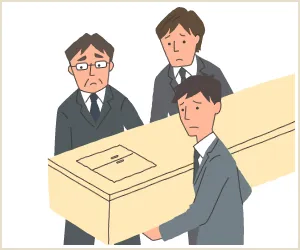
11. 出棺
棺はご遺族や近親者、親しかった友人など、原則として男性の手で運び出します。喪主が位牌を持って先頭に立ち、喪主に次ぐ人が遺影を持って続き、棺を先導します。
-

12. 火葬
棺を安置した祭壇の前で、「納めの式」が行われます。火葬には40分~1時間半ほどかかります。火葬が済んだお骨を遺族や同行者の手によって、骨壷に納めます。
-
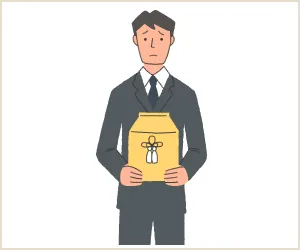
13. 遺骨を持って帰宅する
骨上げが終わると、骨壷は白木の箱の中に入れられ、白布で包んで喪主に手渡されます。このとき、箱の中に埋葬許可証を入れてくれるのが一般的です。これは埋葬するときに必要になるので、このまま大切に保管するようにしましょう。遺骨は喪主が抱きかかえ、その両側に位牌と遺影を持ったほかのご遺族が座り、喪主の車を先頭にして帰宅します。
-

14. 初七日の法要を営む
「初七日の法要」は、故人が亡くなった日から数えて7日目に行なうのが正式です。しかし最近では、遠隔地から訪れる親戚などに配慮して、葬儀の当日、骨上げ後に済ませてしまうことが多くなっています。会食の前には、喪主が簡単にあいさつを述べます。
-

15. 葬儀費用の清算
ご葬儀の翌日以降に、葬儀社から概算の金額と集金の日程の連絡が入ります。
-

16. 葬儀後の諸手続き
故人がそれまで契約していたさまざまなものに名義変更の必要が生じてきます。とくに故人が世帯主であった場合、土地や住まいの名義変更も遺産を相続される人が行わなければなりません。また生命保険や健康保険、年金、預貯金、各種保険のほか、電気、ガス、水道、電話など、故人の名義になっているものはすべてその継承者の名義に変更します。
-

17. 忌明け法要
四十九日法要(四十九日法要はお寺又は葬儀社にご相談ください)仏教では、四十九日目に故人の魂がわが家から離れると考え、遺族は四十九日の忌明けの法要を営みます。それまでは、遺族はお祝い事への出席を控えます。






