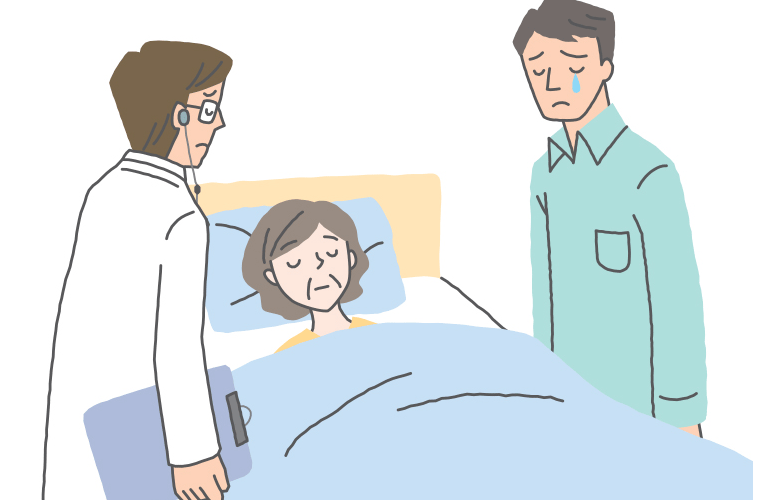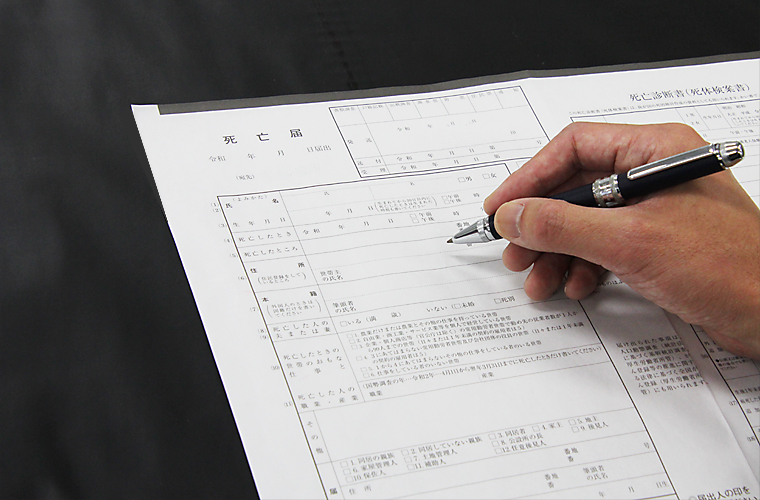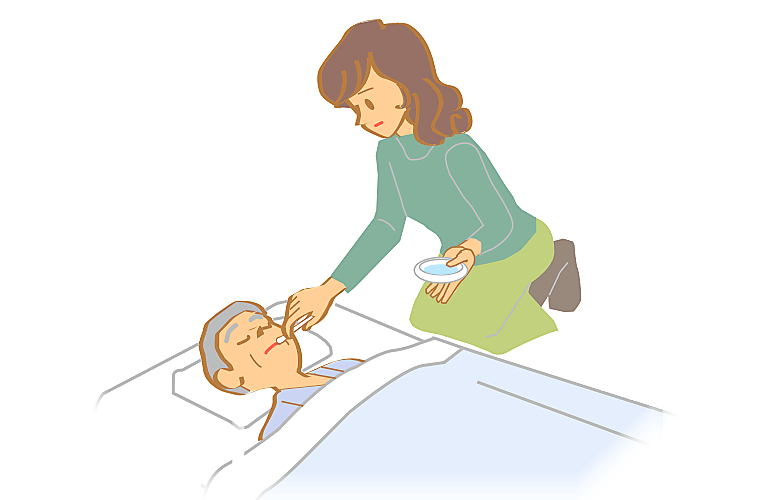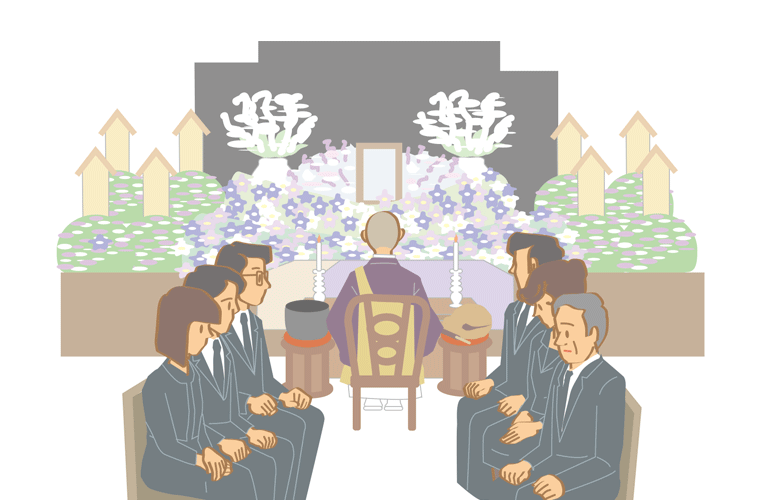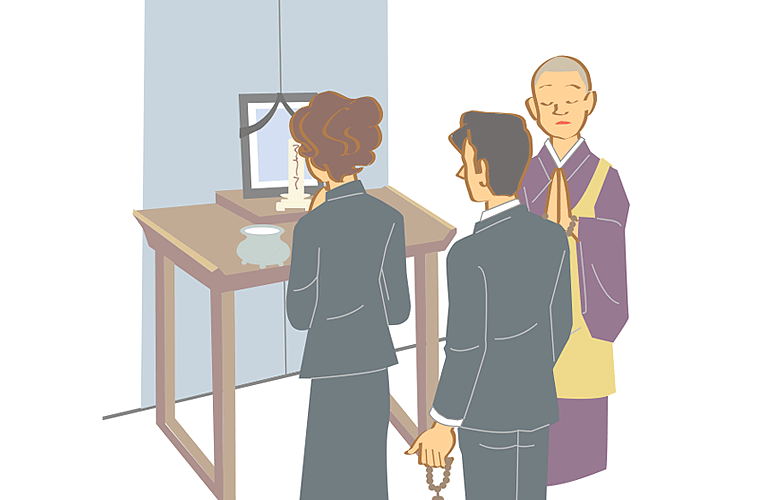2021年 04月 20日(火)
危篤とは?病院から家族の危篤連絡を受けたら?するべきことや考えておくこと
2025年5月15日更新。病院から危篤の連絡を受けたら、誰しもが冷静ではいられないはずです。しかしそんな中でも、親族への連絡や職場への対応など、しなければならないことはたくさんあります。このページでは大切な方が危篤を迎えた時にしなければいけないことや心構え、考えておきたいことをご紹介します。少しでもあなたの支えになればと思います。ぜひ参考にしてみてください。また、非常に考えたくないことだとは思いますが、状況に応じて もしもの時を迎えた場合の直後に行うこと 年末年始にもしもの時を迎えた場合 についてもご参考ください。なお、知人・友人が危篤の場合は 知人・友人が危篤の場合の面会/お見舞い をご参考ください。 事前のご相談もお受けしております。 お気軽にご相談ください。 【もくじ】 1.危篤とは? 1-1「重篤」よりさらに深刻な状態 1-2自宅療養中に容態が悪化したら 2.病院から危篤の連絡を受けた場合にすること 2-1親族へ連絡する 2-2職場へ連絡する 2-3病院へ急ぐ 3.家族にできること 3-1大切な方のそばに寄り添う 3-2想いを伝える 3-3医師や家族・親族間で今後について相談する 4.もしもの時に備えて考えておくこと 4-1菩提寺を確認し相談する 4-2葬儀社を検討する 4-3まとまった現金を手元に置いておく 5.危篤の連絡を受けたら、周囲の協力を得て出来る限りのことをしましょう 1.危篤とは? 危篤とは命に危険が迫り、予断を許さない状態のことです。 病状の悪化や事故など、ひとことで危篤と言ってもその内容はさまざまです。緩やかに健康状態が悪化していくケースだけでなく、容態悪化と小康状態を繰り返すなど、不安定な時期が続く場合もあります。また、危篤状態から回復することもあります。 1-1「重篤」よりさらに深刻な状態 「危篤」と同じような意味を持つ言葉に「重篤」があります。どちらも病状の重い様子を表す言葉ですが、「危篤」という言葉の方がより予断を許さない状況で使われます。 医師の間では、命に危険な迫っている状態をご家族へ明確に伝えるため「危篤」を使用することが推奨されています。そのため病院から危篤の連絡があった場合、文字通り大変な状態であるといえます。 1-2自宅療養中に容態が悪化したら もしも自宅療養中に容体が悪化したら、主治医やかかりつけ医に至急連絡をとりましょう。 また日曜・祝日などで連絡がとれない場合は「119番で救急車を呼ぶ」「ケアマネージャーや介護ステーションに連絡する」などで対応します。 目次に戻る 2.病院から危篤の連絡を受けた場合にすること 2-1親族へ連絡する 危篤である旨を親族に連絡します。急を要する大切なことなので、できる限り電話で直接伝えるようにしましょう。 ■親族へ伝える項目 ●危篤者 ●危篤者の状態 ●入院先の病院名 ●病院の住所 ●面会の可否と詳細 <どの範囲まで連絡するか> 危篤状態の方から見て、3親等まで連絡するのが一般的です。 1親等が親子、2親等が祖父母と孫、3親等が叔父叔母(伯父伯母)や甥姪に当たります。もちろん、3親等内でなくても、特に関わりの深かった方や、最後に直接会わせてあげたいという方がいれば連絡しても構いません。 <遠方にいる親族への連絡> 危篤者との関係性によって判断しますが、いずれにせよ一報を入れておくのがよいでしょう。危篤連絡は来訪を促すものだけではありません。報告として事前にお伝えだけすることも考えてみてください。 なお遠方にいる方をお呼びする場合、宿泊費の立替といった対応も必要になるかもしれませんが、その際には適宜対応しましょう。 <あまり交流のない親族への連絡> 連絡を遠慮することもありますが、「連絡するべきかどうか」と悩んでいるのであれば、その相手にはぜひ連絡しましょう。「あの時、連絡しておけばよかった」という後悔が残らないようにしましょう。 無理に面会を促す必要はありません。どうしても面会がはばかられるという場合は、今の状況だけでもお伝えしておきましょう。 <電話以外での連絡について> もしも電話がつながらないようであれば、メールなどを用いて知らせましょう。 ■親族への危篤連絡のメール文例 件名:【ご連絡】父が危篤になりました。 花子さん 太郎の息子の一郎です。かねてより闘病中だった父の容態が急変し危篤状態になったと連絡を受けました。医師には今日か明日が山と言われています。 よろしければ、父に一目会っていただけないでしょうか。花子さんがいらしてくれたら、父もさぞ喜ぶと思います。 入院している病院は、●●県●●市の●●病院●号室です。 取り急ぎのご連絡です。状況を見てまたご連絡させていただきます。よろしくお願いします。 儀式 一郎 2-2職場へ連絡する <まずは一報を入れる> 危篤の連絡を受けたら、すみやかに職場へ連絡します。仕事を休まなければならない場合は、その旨も併せて伝えましょう。電話で連絡するのが基本です。 「深夜」「未明」など電話がはばかられる時間帯であれば、まずはメールまたはLINEで一報を入れ改めて電話します。 ■職場(上司)への危篤連絡のメール文例 件名:【ご連絡】父が危篤のため、お休みをいただきます 佐藤課長 夜分遅くに大変申し訳ございません。 私事で恐縮なのですが、父の危篤連絡を受けたため数日の休みをいただきたく、ご連絡いたしました。 急なことで大変申し訳ございません。場合によっては休暇が伸びることも考えられます。また状況がわかり次第ご連絡させていただきますが、ご迷惑をおかけすることご容赦ください。 夜分遅いこともあり、取り急ぎメールにて連絡させていただきました。詳細につきましては、明日の午前中にお電話にてお伝えいたします。 何卒よろしくお願いいたします。 儀式 一郎 <状況が整理できた段階で詳細を連絡する> 病院へ到着した後、大切な方の容態がある程度分かった段階で詳細を連絡します。電話での連絡が基本です。 見通しのつかない状況が続き、長期的に休む必要がある場合は、あらためて上司に相談しましょう。 <事前にやっておくと良いこと> 家族が入院していることを上司や部署内に相談しておくとよいでしょう。事前に部署内で状況を共有してもらうことで、もしもの時に引き継ぎなどの対応がしてもらいやすくなります。 また危篤での休暇取得は忌引きには当てはまらないので、有給休暇の取得状況を確認しておくと安心です。 2-3病院へ急ぐ 親族・職場へ連絡したら、至急病院へ駆けつけます。危篤後は状況がどのように変化するか分からないので、自宅と病院に距離がある場合は、着替えや現金(交通費・滞在費)の準備もしておきましょう。 目次に戻る 3.家族にできること 危篤の連絡を受けた後は、「自分にできることは何かないか」と思う方も多いのではないでしょうか? ここでは危篤状態にある方へ、家族としてできることをまとめました。それぞれ詳しくご紹介します。 3-1大切な方のそばに寄り添う そばに寄り添うことで、危篤状態にある大切な方へ安らぎを与えられます。これはあなたにしかできないことです。 症状や容態に合わせて、「語りかける」「手を握る」「身体をさする」などスキンシップをとるのもよいでしょう。 危篤状態と言ってもその症状はさまざまです。意識をなくしていることが多いですが、それ以外にも朦朧としていたり、一時的に回復し、食べ物や飲み物を欲したりすることもあります。 寄り添いながらも、状況に応じて医師の許可のもとケアをしてみましょう。 3-2想いを伝える 危篤状態では視覚を含め多くの感覚が低下していきます。しかしその中でも、聴覚は比較的最後まで失われないと言われています。 仮に反応がないとしても、その言葉は大切な方へ確実に届いています。大切な方への想いを耳元で目一杯言葉にしてあげてください。 3-3医師や家族・親族間で今後について相談する 治療など今後について、家族で意思決定が必要な場合もあります。医療従事者の方や家族間で相談し、納得のいく答えを出せるとよいでしょう。 大切な方が危篤状態にある時は、不安や緊張から冷静な判断ができない場合が多いので、一人で答えを出すよりも、様々な方とのコミュニケーションを多くとることで、満足のいく意志決定につながります。 目次に戻る 4.もしもの時に備えて考えておくこと 「もしもの時に備えた準備や行動は不謹慎だ」と思われる方がいるかもしれません。 しかし事前に考えておくことにより、もしもの時に判断しなければならないことが減るので、その分だけ気持ちの面での負担も変わってきます。 4-1菩提寺を確認し相談する もしもの時に備えて、関係のある菩提寺の連絡先を確認しておきましょう。 できれば連絡もして、「大切な方が危篤状態であること」「葬儀を依頼するかもしれないこと」を伝えておきましょう。菩提寺側も心構えができ、もしもの時に都合を合わせやすくなります。 菩提寺が遠方にある場合は、菩提寺に連絡して指示を仰ぎましょう。遠方でも熱心に出向いてくださる僧侶はたくさんいらっしゃいます。反対に「菩提寺は遠方なので僧侶は来てくれないだろう」と勝手に判断するとトラブルの元になるので注意しましょう。 4-2葬儀社を検討する 病院で最期を迎えた場合、故人様を病院内に長く安置できない場合が多く、速やかな搬送を求められます。 搬送は葬儀社に依頼するのが通常です(搬送用の車両を持っており、経験も豊富なため)。 病院側が紹介してくれる葬儀社に、搬送の流れでそのまま葬儀も依頼してしまう場合が多いですが、必ずしも適した選択とは言えない場合もありますので、どこの葬儀社にお願いするか考えておくと安心です。 4-3まとまった現金を手元に置いておく もしもの時には、すぐに支払いが必要なものもあります。 例えば、公営斎場を利用した場合の費用(火葬料・斎場使用料など)や、菩提寺とは別の僧侶を手配した場合のお布施(読経に対するお布施など)は、その場で支払うことが通常となっています。 また もしもの時を迎えた場合の直後に行うこと 年末年始にもしもの時を迎えた場合 についてまとめました。状況に応じてご参考ください。 目次に戻る 5.危篤の連絡を受けたら、周囲の協力を得て出来る限りのことをしましょう 病院から大切な方の危篤連絡を受けた後にまずやることは、基本的には 「親族・職場への連絡」「病院へ急ぐ」「大切な方の側に付き添う」の3つです。 大切な方が危篤状態になると、ある程度覚悟していたとしても、大きく動揺してしまうものです。「自分がしっかりしなければ」と気丈に振る舞おうとする方もいらっしゃいますが、無理をする必要はありません。 周囲の人に相談して協力を得ながら、「大切な方と一緒にいる時間」を第一に考えて行動しましょう。 24時間365日、ご相談を受け付けております。早朝・深夜、祝日・連休・年末年始も、気兼ねなくご連絡ください。全国儀式サービス コールセンター 事前のご相談も受付しております。■メールお問い合わせページから相談する